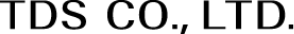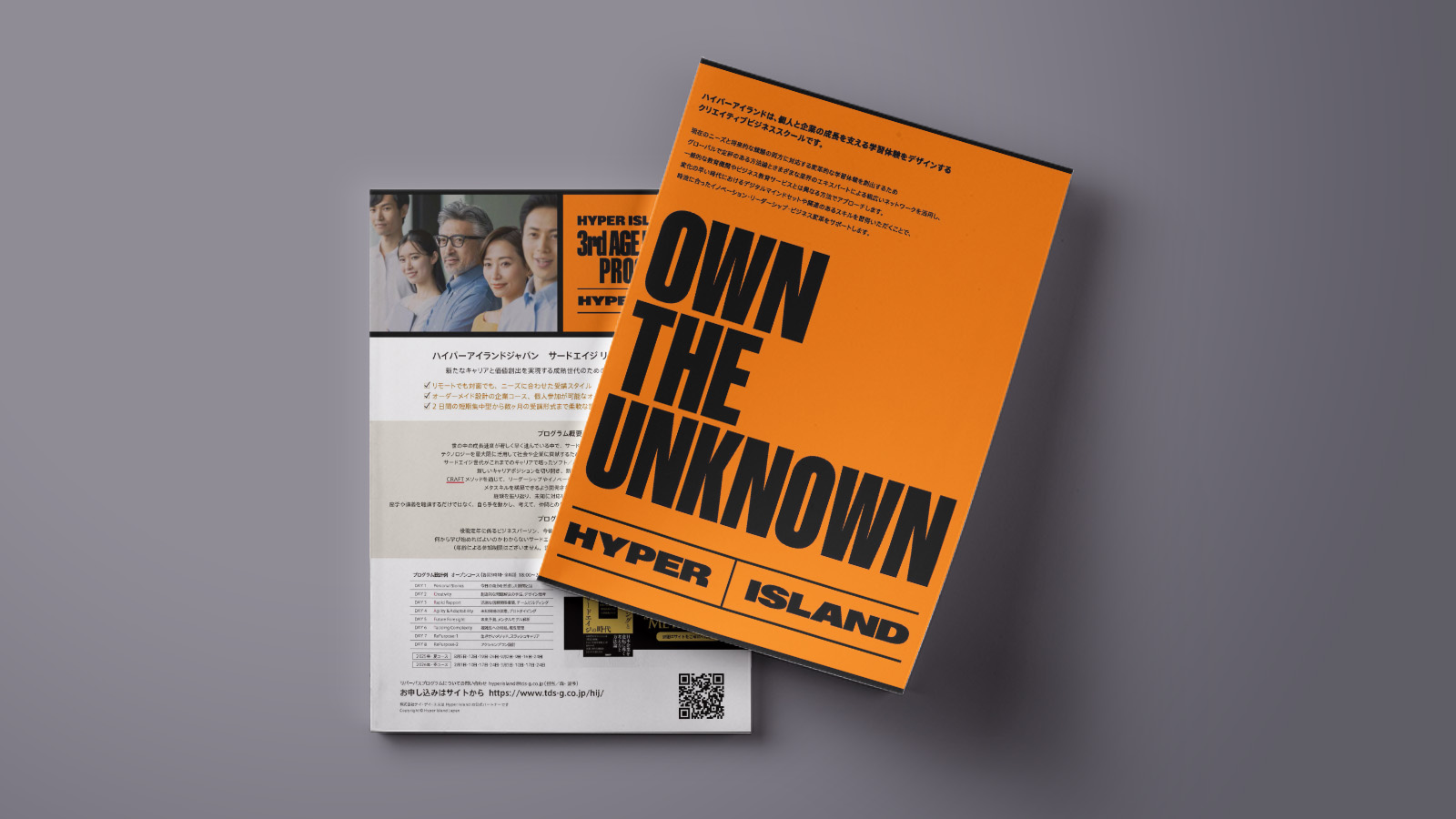静かな退職とは?広がる背景やリスク、組織が取るべき対策を解説
近年、職場で静かに存在感を薄める「静かな退職(Quiet Quitting)」という働き方が注目を集めています。単なる怠けや無気力とは異なり、背景には時代の変化と個々人の価値観の揺らぎが見え隠れしています。
この記事では、静かな退職が広がる背景と組織ができる対策について考えます。
「静かな退職」とは
「静かな退職(Quiet Quitting)」とは、「会社を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働くのではなく、最低限やるべき業務だけをこなす働き方」を指します。2022年にアメリカのキャリアコーチが発信した概念で、最近では日本でも注目されるようになりました。
この考え方が広まった背景には、欧米社会における学歴やキャリアコースによる人生の固定化、努力に見合わないリターンへの失望、そして過度な成果主義への反発があります。必ずしもモチベーションが低いわけではなく、無理に上を目指すのではなく、自分らしいペースで働くことを選択する意識の表れといえるでしょう。
日本では、コロナ禍による働き方の見直しや、仕事中心の価値観からの離脱を志向する若い世代を中心に共感を集めるようになりました。
静かな退職をしている人の特徴としては、指示された業務はこなすものの、それ以上の積極的な提案や残業、昇進を目指す行動には消極的であることが挙げられます。必ずしもモチベーションが低いわけではなく、自分なりの働き方を守ろうとする意識の表れとも言えるでしょう。
「静かな退職」が広がっている理由
静かな退職は、単なる個人の選択にとどまらず、社会全体や組織のあり方を映し出す現象でもあります。
ここでは、特に日本において静かな退職が広がる背景として指摘されている主な要因を紹介します。
過重労働や評価制度への不信感
長時間労働が常態化する一方で、努力に見合う評価や報酬が得られないと感じるケースが増えています。
特に、成果だけを基準とする機械的な評価制度では、働く意欲が失われやすくなります。
というのも、実際の仕事には、成果に直結しない下準備やチームサポートなど、目に見えにくい貢献が多く存在します。成果だけを重視する運用では、こうした努力が評価されず、やりがいや意義を感じにくくなってしまうのです。
さらに、成果は本人の努力だけでなく、市場環境や顧客状況といったコントロールできない要素にも大きく左右されます。
「どれだけ努力しても自分ではどうにもならない」と感じたとき、働くモチベーションは大きく低下してしまいます。さらに、成果主義が極端になると、失敗を恐れてリスクを取らなくなり、短期的な成果だけを追う消極的な働き方に陥りやすくなります。
キャリアの先が見えないことによるモチベーション低下
目の前の業務をどれだけこなしても、将来的な昇進やキャリアアップのビジョンが見えにくい環境では、長期的なモチベーションを保つことが難しくなります。
とくに、キャリアパスが不透明であったり、評価基準が曖昧な組織では、モチベーションを見出しにくくなります。
努力の方向性や到達点が見えないまま働き続けることは、心のエネルギーを少しずつすり減らしていく行為でもあります。
こうした状況が続くと、次第に「頑張っても報われない」という感覚が積み重なり、より大きな目標を目指すことよりも、自分を守るために最低限の仕事だけをこなす状態になりやすい傾向があります。
リモートワークの影響
コロナ禍以降、リモートワークが急速に広がったことで、働く場所や時間に対する感覚が大きく変わりました。
柔軟な働き方が可能になった一方で、会社への帰属意識や同僚との一体感が薄れ、組織への貢献実感を持ちにくくなった側面も指摘されています。
また、リモート環境では日常的なコミュニケーションやフィードバックの機会が減少し、成果や成長が見えにくくなることから、働きがいを感じづらくなる傾向があります。公私の境界線が曖昧になりやすく、仕事への集中や情熱を保つことも難しくなりがちです。
こうした要素が積み重なることで、働き手は「これ以上頑張る必要はない」と感じるようになり、最低限の業務だけをこなす静かな退職のスタイルへと自然に移行していくリスクが高まっているのです。
マネジメントの形骸化、エンゲージメント低下
リモートワークの普及によって物理的な距離が広がっただけでなく、もともと存在していたマネジメントの課題が顕在化しやすくなっています。
従来型の管理重視のマネジメントでは、部下の成長支援や仕事の意義を共有する働きかけが十分に行われないケースが少なくありません。
こうした環境では、働く意義を見いだせず、組織へのエンゲージメントが低下していきます。
上司や組織に期待できないと感じた社員は、キャリアへの投資や積極的な関与をやめ、最低限の業務だけをこなす静かな退職へと移行するリスクが高まります。
ライフステージの変化
結婚、出産、介護といったライフステージの変化に伴い、働き方に対する優先順位が変わることも、静かな退職の背景のひとつと考えられます。
以前から、家庭やプライベートの事情に応じて仕事への比重を調整する動きは存在していましたが、近年では「仕事中心であるべき」という価値観自体が揺らぎ、「今は仕事を最優先にするタイミングではない」と意図的に最低限の働き方を選ぶことが、より自然な選択肢として受け止められるようになりました。
ライフステージに応じた柔軟な働き方を求める声の高まりも、静かな退職という働き方のスタイルを後押ししている要素の一つです。
従業員の「静かな退職」がもたらすリスク
静かな退職は、必ずしも悪い選択とは限りません。
ライフステージの変化や、自分の人生を大切にするために選ぶケースもあり、個々の働き方の多様化として受け止めるべき側面もあります。
しかし一方で、組織全体の視点で見ると、静かな退職が一定数生じることで、目に見えにくい形で影響が積み重なり、結果的に組織運営にリスクをもたらすこともあるため注意が必要です。
ここでは、静かな退職が組織にもたらしうるリスクについて解説します。
生産性の目に見えない低下
静かな退職では、従業員は最低限の業務はこなすため、表面的には業務が回っているように見えます。しかし、本来発揮されうる創意工夫や主体的な改善提案が生まれにくくなり、チーム全体の生産性がじわじわと低下する可能性があります。
目に見えないところでのパフォーマンス低下は、短期的には気づきにくいため、気づいたときには組織全体の力が落ちていた、というリスクをはらんでいます。
組織の挑戦文化が失われる
静かな退職が増えると、「無理をしてまで新しいことに挑戦しない」「現状維持で十分」という空気が職場に広がることがあります。
挑戦を推奨する文化が弱まると、結果としてイノベーションや成長機会が失われ、組織の活力そのものが萎縮してしまう危険性があります。
他社員への影響
周囲に静かな退職状態の社員が増えると、他の社員にも少なからず影響が及びます。
「頑張っても報われない」「頑張らなくても許される」という空気が広がると、チームの士気や組織文化自体が徐々に弱まっていく可能性があります。
特に若手社員や中堅社員にとっては、周囲の働き方が「普通」になりやすく、職場全体のモチベーション低下に拍車をかけてしまうリスクもあります。
離職予備軍の可能性
静かな退職を選んでいる社員の中には、すでに心理的には離職に向かっている「サイレントフライト(静かな離脱)」状態の人も含まれている可能性があります。
目立った不満を表に出さないため、周囲からは気づかれにくいものの、突然の退職につながるケースもあり、組織にとっては大きな痛手となるリスクがあります。
静かな退職の対策──リスキリングと“静かな採用”で組織を再活性化
静かな退職(Quiet Quitting)は、単なる「怠け」というわけではありません。
背景には、「頑張っても報われない」「働く意義が感じられない」「自分の可能性が閉ざされている気がする」といった、心理的な無力感や無関心が横たわっています。
だからこそ、適切に「自分にしかできない役割」や「新たな成長の可能性」に気づける機会を提供できれば、再び心を動かし、主体的な働き方へと戻る人も一定数存在します。静かな退職を一律に否定するのではなく、一人ひとりの選択や状況を尊重しながら、組織として柔軟に支援策を用意することが求められています。
ここでは、具体的な取り組み例について紹介します。
キャリアの再設計の機会を設ける
静かに退職している社員の中には、「この先、自分がどう働き、どんな成長を目指せばいいのか」が見えなくなっている人も少なくありません。
そこで、1on1ミーティングや研修などを通じ、個々のキャリアビジョンを再設計する機会を積極的に設けることが有効です。
リスキリングの機会を与える
リスキリングとは、業務の再定義や社会の変化に応じて新たなスキルを獲得し、職務やキャリアを再構築する取り組みを指します。
静かな退職状態にある社員の中には、「何に貢献しているかわからない」「自分の可能性が閉ざされたように感じる」といった“内なる迷子”状態にある人も多く存在します。
こうした社員に、自分の強みを再発見し、新たなスキルや役割に目を向ける機会を提供することは、再び組織とのつながりを取り戻すきっかけになり得ます。
静かな採用
静かな採用とは、社外から新たに人材を採用するのではなく、社内に既にいる社員に対して新しい役割やチャレンジの機会を与える考え方です。
一見やる気を失っているように見える社員であっても、
「自分の強みが活かされていない」
「本当にやりたい仕事に就けていない」
「成長機会を得られていない」
といった理由で静かにエンゲージメントを下げている可能性があります。
こうした人材に「別のミッション」を与え、社内で“再採用”するような発想が、静かな採用
なのです。
実際に、リスキリングと静かな採用を組み合わせた施策によって、
・技術職から営業支援職へ転換し、コミュニケーション力を発揮して活躍
・管理職を希望していなかった社員がプロジェクトマネジメントで覚醒
・埋もれていた専門スキルが横断的プロジェクトで再評価される
など、新たな可能性を引き出す成功事例も生まれています。
なお、キャリア再設計とリスキリングを同時に支援する取り組みの例として、ハイパーアイランドが提供する「サードエイジ リパーパスプログラム」があります。
このコースでは、キャリアの棚卸しによる自己理解と、これからの時代に必要なメタスキルの習得を組み合わせることで、再び自らの可能性を広げ、主体的にキャリアに向き合うきっかけを提供しています。
サードエイジ世代を対象としたプログラムですが、キャリアの節目を迎えるすべての人にとって、これまでの経験を生かしながら次のステージへ進むヒントが得られる内容となっています。興味がある方は、ぜひ詳細をご覧ください。
また、ハイパーアイランドではこのほかにも、さまざまな世代・テーマに対応したリスキリング・キャリア支援プログラムを展開しています。
まとめ
静かな退職(Quiet Quitting)は、単なる怠けや無気力ではなく、「頑張っても報われない」「働く意義が感じられない」「自分の可能性が閉ざされている気がする」──
そんな心理的な無力感や無関心が背景にある現象です。
すべての静かな退職者が再び意欲的に働き始めるわけではありませんが、適切なキャリア再設計の機会やリスキリングの支援、新たな役割提案(静かな採用)を通じて、再び主体的にキャリアに向き合おうとする人たちも少なくありません。重要なのは、静かな退職を一律に否定するのではなく、個々人の選択やタイミングを尊重しながら、再エンゲージメントのきっかけとなる機会を組織として柔軟に用意していくことです。
静かな退職が社会に広がる今だからこそ、「個人」と「組織」が対立するのではなく、お互いを尊重しながら新たな活力を生み出す視点が求められています。
詳しい資料はこちらからダウンロード!

Hyper Island Japanチーム
北欧発のビジネススクール「Hyper Island」の日本チームです。
Hyper Islandのメソッドや思想をもとに、企業や個人の学びにつながる情報を発信しています。