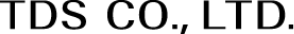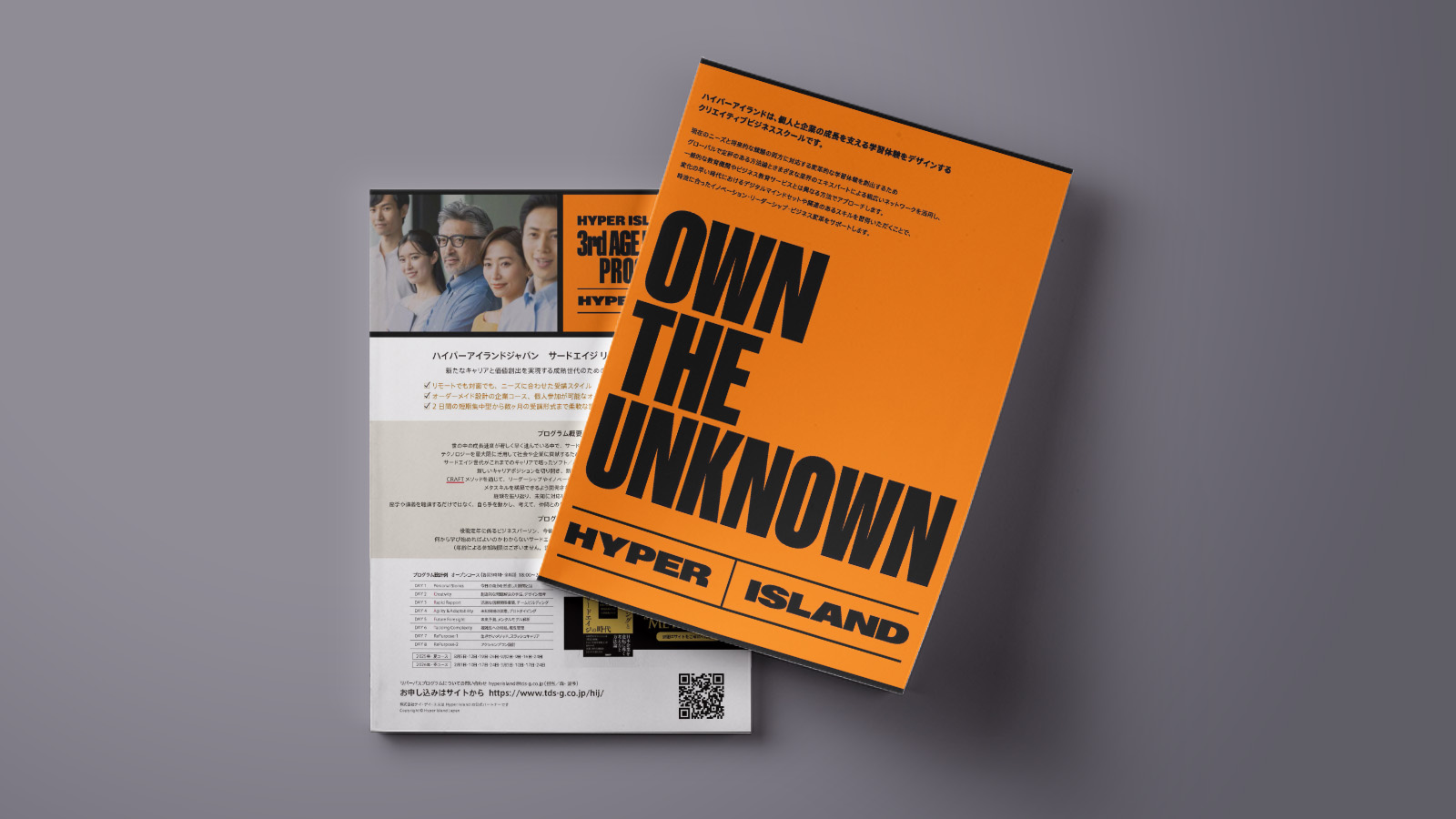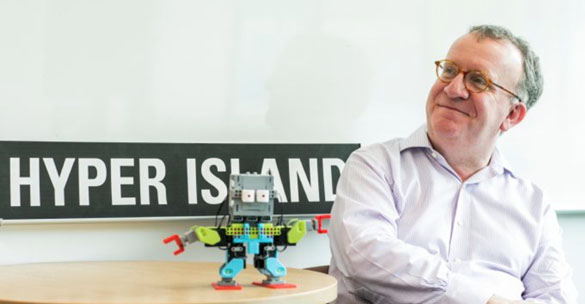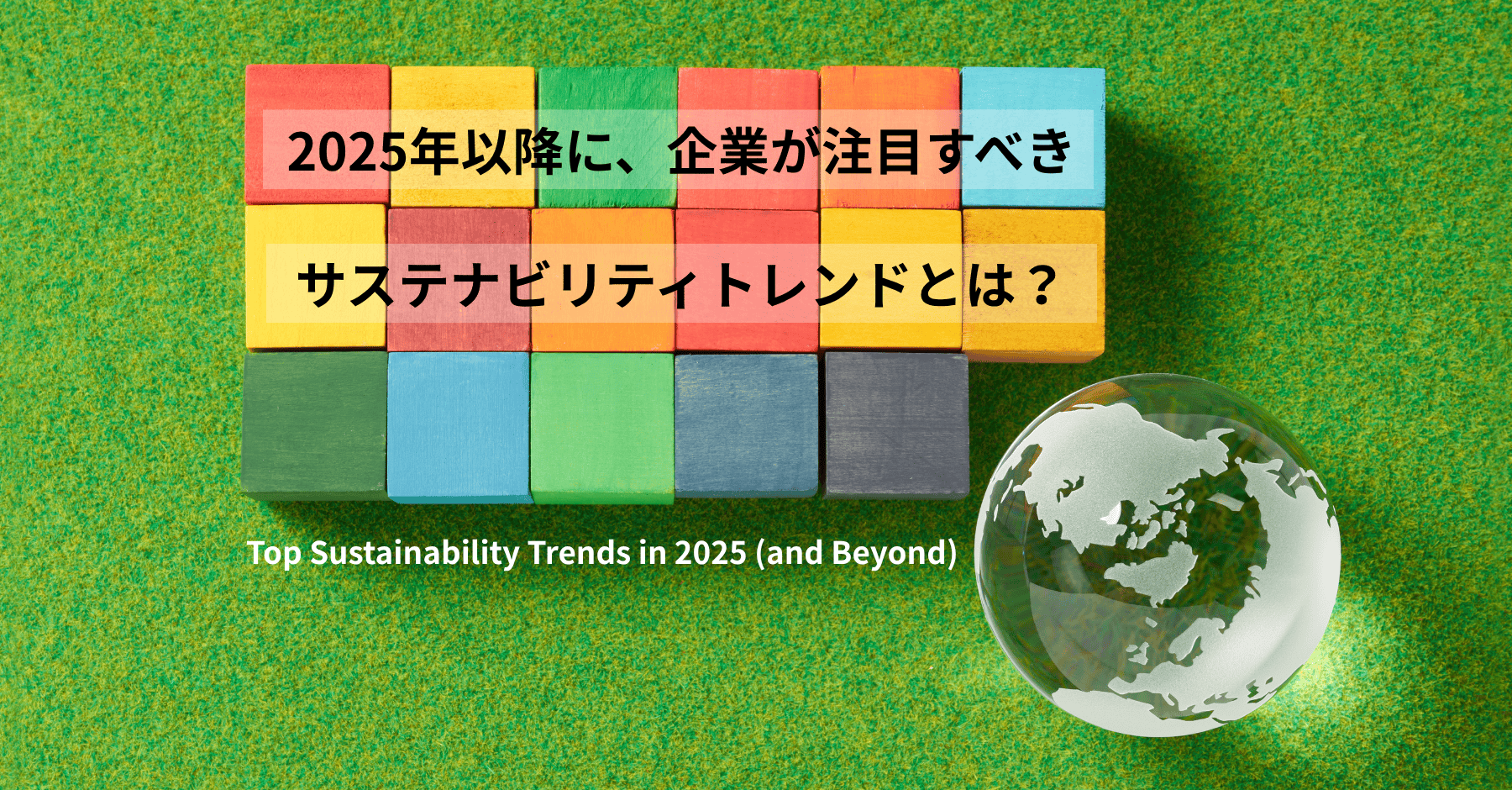
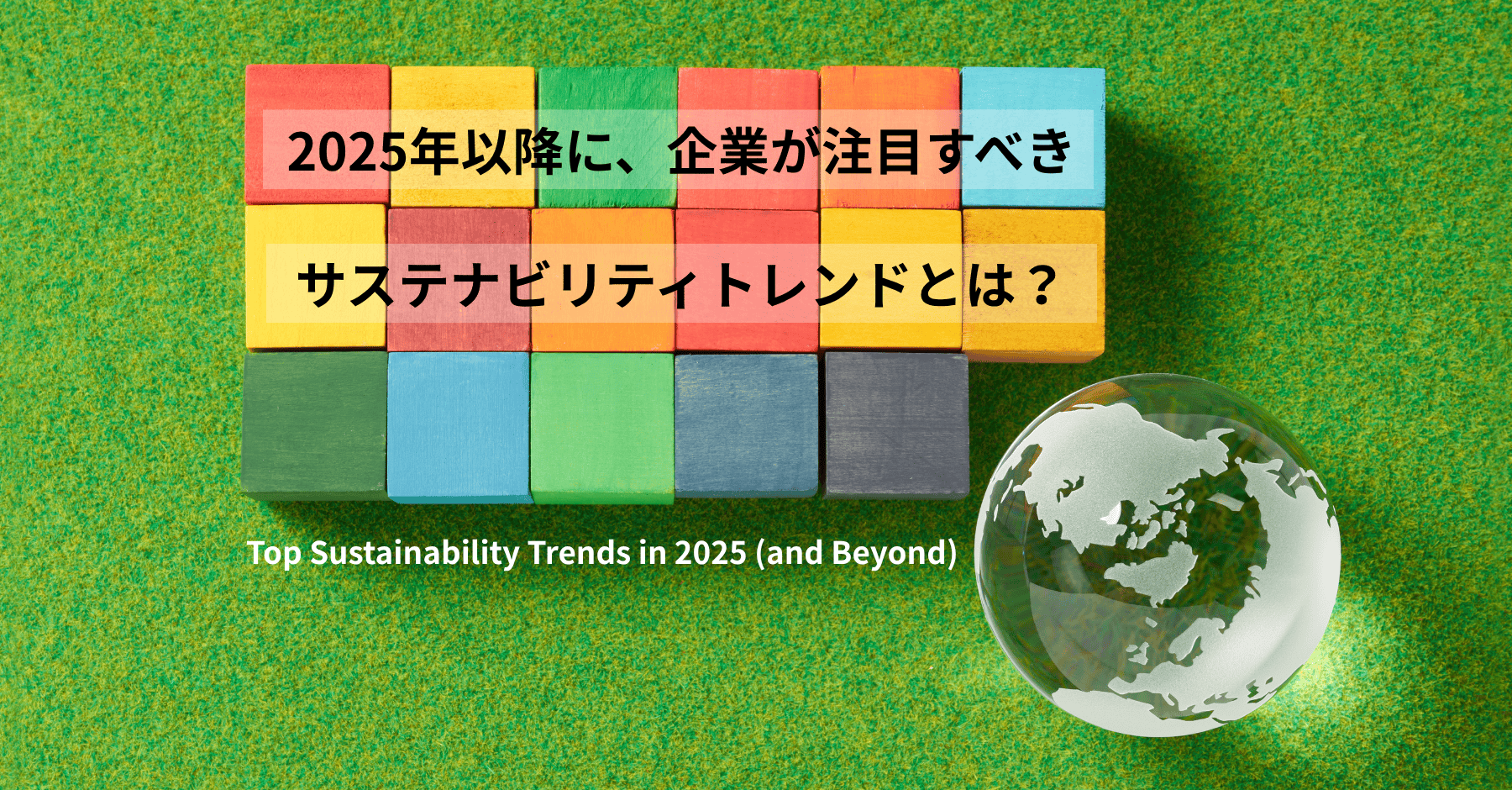
2025年以降に企業が注目すべきサステナビリティトレンドとは
サステナビリティは急速に進化し、2025年の企業経営における基盤となりつつあります。
顧客・従業員・投資家からの期待が高まり続ける中、もはやサステナビリティを「あると良いもの」として扱う時代ではありません。
今やそれは、企業が“時代に適応し、信頼され、持続的に成長する”ための戦略的な必須要素となっています。
本記事では、2025年以降におけるサステナビリティの主要トレンドと、その重要性について解説していきます。
なお本記事は、Hyper Island Global Blog「Top Sustainability Trends in 2025 (and Beyond)」(原文英語)をもとに、筆者の視点で意訳・再構成したものです。
サステナビリティにおける7つの主要トレンド
1. サーキュラーエコノミー:長寿命設計と再利用の発想
より多くの企業が、従来の「取る・作る・捨てる」という線形型モデルから脱却し、サーキュラーエコノミー(循環型経済)という、より賢く持続可能な生産・消費のあり方へとシフトしています。
短いライフサイクルを前提にした製品づくりではなく、再利用・修理・再生・リサイクルを通じて、できる限り長く素材を循環させることに焦点を当てるのがこのモデルです。
この取り組みにより、企業は廃棄物の削減や環境負荷の軽減を実現するだけでなく、既存の資源からより大きな価値を生み出すことができます。
IKEAやPatagoniaといったブランドはすでに、製品設計、再販モデル、素材調達の各プロセスに「循環性」の概念を組み込み始めています。
そして2025年、サーキュラー思考は競争優位の源泉になりつつあります。
原材料価格の高騰や消費者の意識の高まりを背景に、循環型の戦略はコスト削減・レジリエンス強化・サステナブルな企業姿勢の実現を同時にかなえる手段として、ますます重要性を増しています。
2. リジェネラティブ・デザイン:サステナビリティのその先へ
サステナビリティ(持続可能性)が主に「環境への悪影響を最小限に抑えること」を目的としているのに対し、リジェネラティブ・デザイン(再生型デザイン)は、その一歩先を見据えています。
これは、自然環境や社会システムを“回復・再生・向上”させることを目指すアプローチであり、エコシステムの保全や土壌の健康改善、生物多様性の拡大など、「使う以上に還元する」発想に基づいています。
たとえば、一部の建築家は、消費するエネルギーよりも多くのエネルギーを生み出す建築物を設計したり、雨水を回収・再利用する仕組みを導入したり、地域生態系を支える屋上緑化を採用するなど、再生型のアプローチを実践しています。
また、農業分野でも、土壌の再生や炭素固定を目的とするリジェネラティブ農法が広がりを見せています。
このようなリジェネラティブ・デザインの考え方は、さまざまな業界に浸透しつつあります。
2025年には、多くの企業が、長期的なレジリエンス(持続的な強さ)とは、単に環境負荷を削減することではなく、自社が依存する環境やコミュニティを積極的に再生していくことにあると認識し始めています。
3. 水資源保全への関心が急速に高まる
水不足は、もはや遠い未来の問題ではありません。
国連や各国の研究機関によると、世界人口のほぼ半数が、年間を通じて一定期間「水ストレス(=水資源の不足)」に直面すると予測されています。
こうした水資源への圧力の高まりを受け、企業はこれまで以上に水の利用を真剣に捉える必要に迫られています。特に製造業・農業・繊維産業などの分野では、水の消費量削減や排水処理の改善が強く求められています。事業継続リスク、規制対応、社会的プレッシャーといった観点から見ても、「何もしない」という選択肢はもはや存在しません。
一部の企業はすでに行動を起こしています。たとえば、ファッションブランドのLevi’s(リーバイス)は、デニム製造工程において「Water<Less®」技術を導入することで、水使用量を大幅に削減しました。
この取り組みは、資源効率の向上とブランド価値の両立が可能であることを証明しています。
2025年以降、企業が「水」を重要な共有資源として位置づけることは、環境制約や社会的要請の中で持続的に成長していくための鍵となるでしょう。
4. グリーンAI革命:環境負荷に向き合う次のステージ
AI(人工知能)はすでに、エネルギー使用量の予測からサプライチェーンの最適化に至るまで、サステナビリティ推進の在り方を大きく変革しています。
一方で、AIには見過ごせない「カーボンコスト(炭素負荷)」が伴います。
大規模なAIモデルの学習には膨大なエネルギーを要し、AIそのものの環境影響が新たな課題として浮上しています。
マサチューセッツ大学の研究によると、ひとつの大規模AIモデルを学習させるだけで、平均的な自動車5台が生涯に排出するCO₂量に匹敵する温室効果ガスが発生すると報告されています(University of Massachusetts Amherst, 2019)。
企業がAIを活用してサステナビリティを推進する一方で、AIの活用によって生じる排出にも責任を持つことが求められています。そのためには、より環境負荷の少ないデータインフラの採用、モデル設計の効率化、そしてAI戦略の初期段階からサステナビリティを組み込むことが不可欠です。
5. 気候関連報告基準の厳格化
気候関連の報告基準は年々厳格化しており、透明性はもはや企業の常識となりつつあります。
政府、規制当局、そして投資家は、企業に対して環境影響をより明確かつ一貫した形で測定・開示することを求め、基準の水準を引き上げています。
特に、EUの「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」や、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)による気候情報開示フレームワークといった国際基準が、グローバルな期待値を形成しています。
これにより、明確な根拠を欠いた抽象的なサステナビリティ主張(いわゆる“グリーンウォッシング”)は、通用しにくくなっています。
こうした基準や規制の強化が進む中で、測定可能な形で進捗を示せる企業は、信頼性と評価を高めることができます。
一方で、十分な準備を怠る企業は、法的リスク、投資家からの圧力、そして評判の低下といった重大な影響に直面する可能性があります。
6. サプライチェーンの透明性は“もはや必須条件”
前項で述べたように、企業に求められる基準はますます高まっています。
そしてその対象は自社の事業活動にとどまらず、サプライチェーン全体のあらゆる段階にまで拡大しています。顧客、規制当局、投資家は今、製品が「どこで、どのように」作られているのかを可視化することを企業に強く求めています。
つまり、企業は単に原材料を調達するだけでなく、サプライヤー、製造業者、流通業者を含む全てのパートナーにおいて、倫理的な労働環境、公正な賃金、環境に配慮した生産体制を確保する責任を負っています。
テクノロジー業界やファッション業界では、FairphoneやPatagoniaといったブランドが先進的な取り組みを行っています。彼らは、サプライチェーンの詳細なデータを公開し、認証済みの倫理的サプライヤーとの協働を通じて、新たな業界基準を打ち立てています。
2025年において、サプライチェーンの透明性を高い水準で実現できる企業は、より信頼され、将来を見据えた“持続可能な企業”として評価されるでしょう。
一方で、その対応を怠る企業は、評判の失墜や規制上のペナルティといったリスクに直面する可能性があります。
7. 拡大するESGスキルギャップ
サステナビリティ戦略の強さは、それを担う人材の質にかかっています。
しかし現在、ESG(環境・社会・ガバナンス)や気候リスク、倫理的報告に精通した専門人材が世界的に不足しており、深刻なスキルギャップが生じています。
企業がサステナビリティ目標を達成し、新たな規制要件に対応するためには、ESGの全体像を理解し、実践できる人材の存在が不可欠です。
LinkedInの「Global Green Skills Report」によると、2015年以降、「グリーンスキル(環境関連スキル)」を要件とする求人は年平均8%以上増加しています。一方で、そうしたスキルを持つ人材の供給は追いついていません。
このデータは「教育や人材育成への投資こそが、実効性のあるESG戦略の中核である」という明確なメッセージを示しています。
サステナビリティは、もはや経営の必須要件
ここまで紹介してきたトレンドが示すように、サステナビリティやESGはもはや「あると望ましい」取り組みではなく、事業のレジリエンス(持続的な強さ)、イノベーション、そして信頼の基盤となっています。
2025年以降に成長を遂げる企業は、すでにその変化への準備を始めています。ビジネスモデルを再設計し、組織全体を巻き込み、企業理念と実践を一致させること。こうした動きが、未来を切り拓く鍵となります。
先進的な企業はすでに、従業員のスキルアップやリスキリングへの投資を進めています。
人材こそが変革の推進力であり、彼らが変化の最前線をリードする時代が始まっています。
あとがき
サステナビリティは、企業の社会的責任を超えて、経営そのものの在り方を問うテーマへと進化しています。
環境・人・組織の持続性をどう確保するかは、もはや一部の部署の課題ではなく、経営層から現場までが共有すべき戦略的テーマです。
この記事で紹介したトレンドは、2025年以降の企業活動における重要な指針を示しています。サーキュラーエコノミー、リジェネラティブ・デザイン、AIやESGの新たな潮流など、どれも一過性のブームではなく、企業が“信頼される存在”であり続けるための新しいスタンダードです。
同時に、これらの変化は「外から求められる対応」ではなく、「内から選び取る姿勢」へと転換しつつあります。
経営の意思決定、社員一人ひとりの行動、パートナーとの協働―そのすべてが、企業のサステナビリティを形づくる要素となります。
Hyper Island本社のあるスウェーデンでは「IDGs(Inner Development Goals(内面の成長目標)」の取り組みが盛んになっており、SDGs(持続可能な開発目標)の達成を支援するために、個人の内面的な成長を促すフレームワークとして世界が注目しています。
これからの時代、サステナビリティは企業の“優先順位のひとつ”ではなく、経営の中心軸です。変化をチャンスと捉え、価値創造へとつなげていくことが、次の時代をリードする企業の条件といえるでしょう。
HYPER ISLANDの関連コース
いま企業に求められているのは、環境対応やレポート作成といった“反応型”のサステナビリティではなく、未来を見据え、自ら変化を設計する“創造型”のアプローチです。
Hyper Islandの「フューチャーシナリオ」コースでは、未来を観察し、複数の可能性を描き出し、戦略へと転換する力を養います。持続可能な未来を“待つ”のではなく、“つくる”ための思考法が、ここにあります。
フューチャーシナリオ
シナリオ・プランニングの手法を知り、変化の速い業界におけるビジネスやデジタル、人的課題に対応するため、変化領域を深く観察し、戦略的予測や提言を行うためのツールやテクニック、手法を学びます。また、問題解決におけるシステム思考についても包括的な理解を促します。
このプログラムを修了すると、組織や社会に今後起こりうる未来について、戦略的な予測と提言を行い、特定された問題に対して、根拠や調査結果をもとに選択肢を明確に提示し、顧客や業界に助言を与えることができます。
https://www.tds-g.co.jp/hij/action_learning/future_scenarios.html
詳しい資料はこちらからダウンロード!

Hyper Island Japanチーム
北欧発のビジネススクール「Hyper Island」の日本チームです。
Hyper Islandのメソッドや思想をもとに、企業や個人の学びにつながる情報を発信しています。