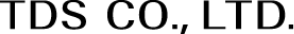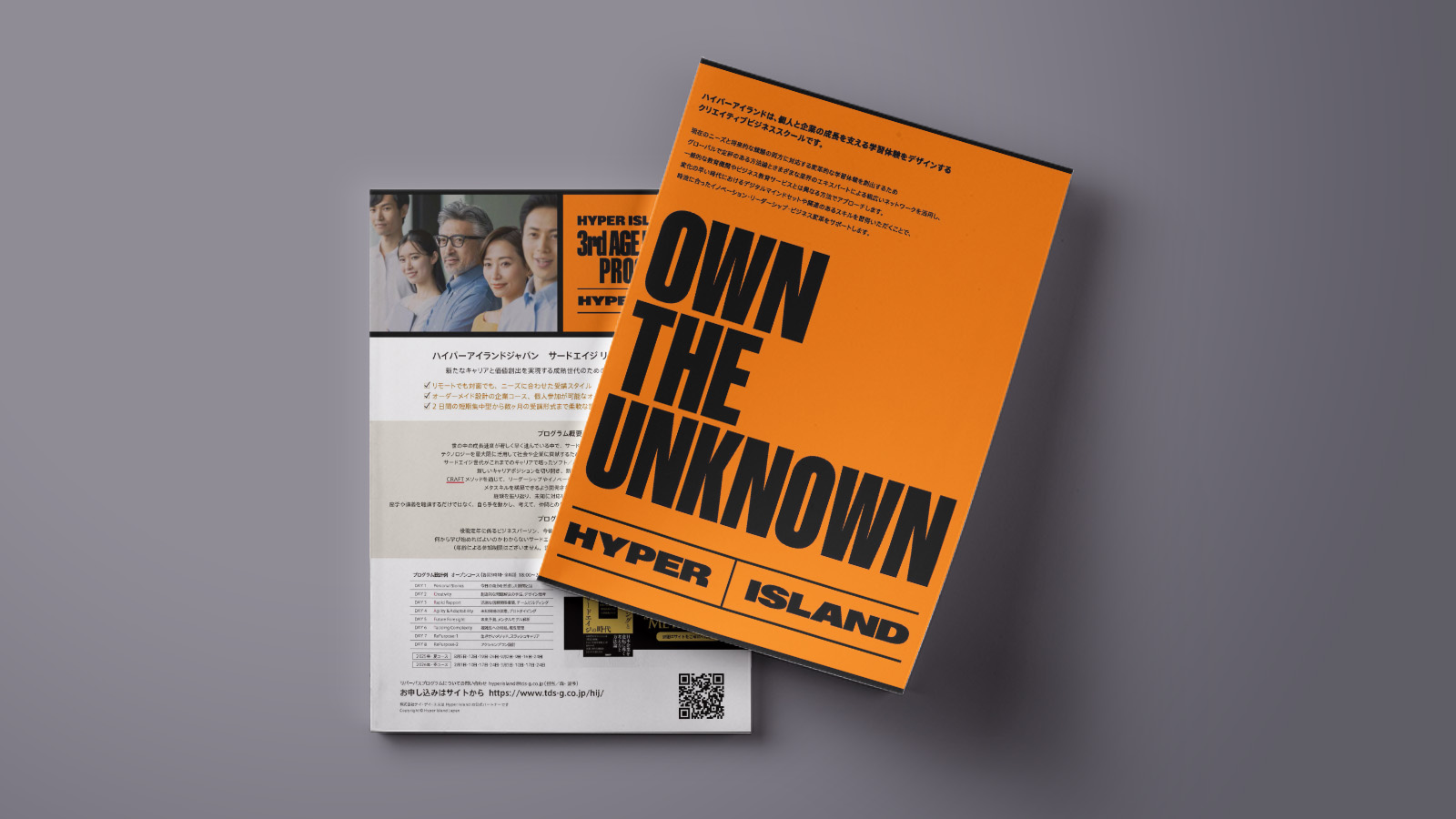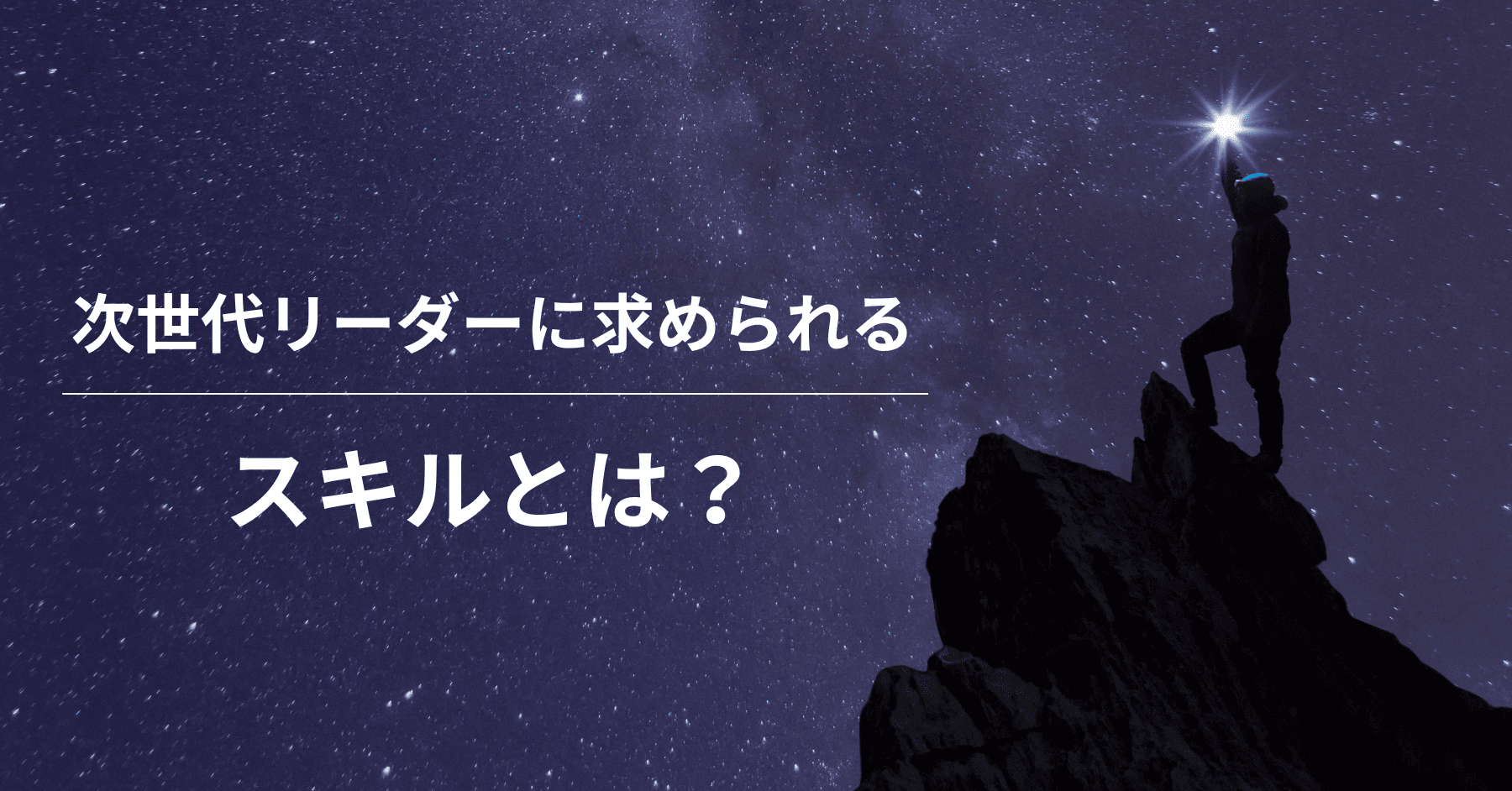今なぜ「サードエイジ」なのか?—— 『逆転のリスキリングとサードエイジの時代』が描く新しい未来
これまで、定年を迎える「成熟世代(サードエイジ世代)」は、徐々に第一線から退き、静かに役割を終えていく存在として見られてきました。
しかし、テクノロジーの進化が加速し、AIが社会に浸透しつつある今――
これからの時代に本当に価値をもたらすのは、むしろこのサードエイジ世代かもしれない。
そうした視点が、今注目を集め始めています。
本記事では、ハイパーアイランドジャパン代表・森杏奈の著書『逆転のリスキリングとサードエイジの時代 企業の成熟世代を知的長寿にする人材育成メソッド』をもとに、その理由を解説していきます。
※本文中の引用は、すべて『逆転のリスキリングとサードエイジの時代 企業の成熟世代を知的長寿にする人材育成メソッド』(森杏奈著)より抜粋しています。
今、私たちはどんな時代にいるのか?
私たちは、今どんな時代を生きているのでしょうか。
本書では、以下の3つの特徴を挙げています。
・カオス化する世界
・技術統合時代の終焉
・成長志向の終焉へ
順番に解説していきます。
・カオス化する世界
政治や経済の分野では、若者がトップに立つ場面が増えています。本書では、その背景に「将来に向けた正しい答えは誰も持っていない」という、現代特有の混沌があるとしています。経験豊富な高齢者であっても確実な判断が難しいからこそ、「迅速に行動できる若い世代」に託すという判断が合理的に映るのです。
複雑で混沌とした世界を表す言葉として、「VUCA」があります。
「Volatile(変動性)」「Uncertain(不確実性)」「Complex(複雑性)」「Ambiguous(曖昧性)」の頭文字からなる言葉で、組織の状況や環境を特徴付ける言葉としてよく使われるようになりました。
近年では、より現代的な混乱を表す言葉として「BANI」という言葉も登場しています。「Brittle(脆弱性)」「Anxious(不安定性)」「Non-linear(非線形)」「Incomprehensible(不可解性)」の頭文字をとったもので、気候変動や社会システムの変化など、より感情や反応を伴う複雑さを捉える概念です。
【関連記事】BANIとは?VUCAに代わる新しい世界を表す言葉
本書では、このような状況下で人々が共通して感じる“焦り”に注目しています。ただし、反応の仕方は人それぞれで、それがさらなる混沌を引き起こしている――。これが、今の時代の本質であるとしています。
❝ここで注目したいのは、その焦りに対する反応に共通点が見られないことです。代表的な反応としては、
・安定した過去にしがみつこうとする。または、諦める
・スキルアップを急いで反応的なトレーニングに励む
・専門分野をより深く掘り下げ、唯一無二な存在を目指す
など、バラバラな反応が起きています。
(中略)
複雑で混沌とした世界から誰もが抜け出したいと思っていますが、一体自分がどう振舞えばよいのかわからず、他の人々の反応がバラバラであるために、混沌度合いはひどくなる一方です。❞
技術統合時代の終焉
本書では、私たちがこれまで技術の進歩によって生活の質を向上させてきた「技術統合時代」を生きてきたと位置づけています。実際、過去150年の技術の進化は著しく、特に直近50年はITを中心に革新が加速しました。今後も技術革新は続くと見られますが、本書では「技術を受け入れる側の変化」に注目しています。
従来は、新技術は「新しいもの好き」から「慎重な多数派」へと段階的に広がるとされ、イノベーター理論に基づいて市場は5つの層(イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティなど)に分類されてきました。
しかし近年では、こうした段階を経ず、急速に浸透する「ビッグバン・ディスラプション」が増えています。生成AI「ChatGPT」はその象徴で、公開から2か月で1億人の利用者を獲得し、AIが単なる技術革新を超えた“パラダイムシフト”であることを示しています。
また本書では、ダノン社やシプラ社といった第4次産業革命の先進企業(ライトハウス企業)が、従業員のボトムアップ活動や教育に力を入れている点に注目。技術の進化が速い現代において、企業の持続的な成長は「人の成長」にかかっているとしています。
❝ライトハウス企業が人材育成に投資するということは、企業活動のすべてが技術に置き換わることはなく、未来も人が重要な役割を果たし、技術と人の共同作業を前提にすると、技術の進化は速いためボトルネックは人であり、人の能力が企業全体の能力を左右する、つまり、「従業員の永続的な成長が企業の永続的な存続を可能にする」と考えているのだと思います。
(中略)
これまでの「技術統合時代」は人の社会をより良くするために技術を生かしていましたが、これからは技術の進化を人が取り込み、人自身がより良くなっていくのです。技術を「活用する」ではなく「取り入れる」感覚であり、自分自身をより良くするために技術を生かすのです。よく言われる「AI共存時代」とは、「社会の中に人とAIが共存」しているのではなく、「人の一部としてAIが共存」することなのです。❞
成長志向の終焉へ
本書では、経済モデルの変化として、イギリスの経済学者ケイト・ラワースが提唱した「ドーナツ経済学」に注目しています。この理論は、「人間の最低限の暮らし」と「地球環境が耐えられる上限」のあいだで経済活動を行うというもので、“誰ひとり取り残さず、かつ地球を壊さない”経済の実現を目指しています。
ドーナツの図では、中心の穴が食料・医療・教育などの「社会的な不足」を、外側の輪が気候変動や生物多様性の喪失といった「環境的限界の超過」を表します。この“ちょうどよい範囲”を保つ経済運営は、アムステルダム市などで実際に政策に取り入れられ始めています。
ラワースはこのモデルのもと、これまでの「成長志向」から、「繁栄志向」への転換を訴えています。ここで言う繁栄とは、尊厳を保ちながら、選択の自由と信頼できるつながりを持つ豊かな暮らしのことです。
❝ここでポイントとなるのが、繁栄志向に必ずしも経済成長が必要なのかということです。発展途上国と先進国では事情が異なりますが、ある程度成熟した先進国では成長が止まるのはネガティブなことではなく、むしろ、繁栄を後押しするという見方があります。成長の限界が創造性の源になり、国や所属している組織への帰属意識を生み出し、何かに参画していく意識を生み出すとされ、そうしたことが人々の繁栄を開花させるという考え方です。❞
とはいえ、こうした考え方はまだ一部の進歩的な経営者層にしか広まっていないのが現状です。
時代の移り変わりを踏まえた未来
本書では、これまでの変化を踏まえた未来像として、「人の能力の限界で不可能だったことが、可能になっていく時代」が訪れると予測しています。技術の進化は止まることなく、今後はむしろ、人が技術によって進化する――そんな時代に入っていくというのです。
たとえば、ドーナツ経済学と目的を共有するSDGsが思うように進まない理由の一つに、「利益につながりにくい」という現実があります。しかし本書では、それを「人の能力の限界」と捉え直します。
もし地球規模の課題を解決しながらビジネスとしての収益も両立できるようになれば、トップ企業はこぞって方向転換し、繁栄志向の経済モデルへとシフトしていく可能性があると指摘しています。
もちろん、これは一つの仮説にすぎません。けれども「技術で人が進化する時代」には、どのようなパラダイム転換が起きるか予測がつきません。だからこそ、その未来をどう形づくるかは、私たち一人ひとりの選択と行動にかかっているのです。
これからの時代に求められる能力とは
こうした時代の到来を前提とするならば、これからの時代に求められるのは、AIと人間が一体となって能力を高め合う“協働の時代”に適応できる人材です。
AIは既知の問題を迅速かつ正確に処理できますが、「何が問題か」を見極める力までは持ちません。だからこそ、人間に求められるのは、問いを立て、意味づけ、創造的に応答する力です。
本書では、AI時代に不可欠な人間の能力として、以下の4つを挙げています:
・問題発見力
・的確な予測
・革新性
・技術を高度に使いこなす能力
さらに、ハイパーアイランドでは、これらを体現する人材像として以下の6タイプを提示しています。
1.SYSTEM CONECTOR(システムをつなぐプロ/N型人材)
2.RAPID ADAPTOR(素早く適応する人)
3.CONFIDEN TEAMER(自信に満ちたチームビルダー)
4.PLAYFUL EXPLORER(遊び心のある探検家)
5.TECH WRANGLER(テックの達人)
6.REFRECTIVE STORYTELLER(思慮深い語り手)
これらについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
【関連記事】未知を味方にする人材の6つの特徴とは?~AI、テクノロジー時代との向き合い方~
❝6つの人材像の共通点は、
- 様々な事象の基礎的なことを理解する
- 全体を俯瞰するマインドセットを構築する
- 挑戦し、変化を起こし、勇気を持つ
となるでしょう。総じて、「好奇心」や「勇気」という人間にとってかけがえのない能力を強調しています。❞
そして、こうした資質を支えているのが、次に紹介する「メタスキル」です。
未来に求められる能力「メタスキル」
ハードスキル、ソフトスキルに続く第3のスキルとして、ハイパーアイランドが注目しているのがメタスキルです。これは「AIにはできない、人間の中核的な力」を意味し、変化の激しい時代において不可欠な能力です。
『Meta Skills』の著者であるマーティ・ノマイヤーは、メタスキルを以下の5つに分類しています:
1.Feeling(感じ取る力、共感力と直感力)
2.Seeing(見通す力、システム思考)
3.Dreaming(夢見る力、実践的な想像力)
4.Making(実現する力、デザイン力)
5.Learning(学ぶ力、新しいスキルを習得する能力)
❝メタスキルを習得するというのは、知識をただひたすら追い求めて賢くなることではなく、自信をもって「私はなんでも学ぶことができる」と言えるようになることなのです。メタスキルの特徴をひと言で表せば「学ぶための学習スキル」といえます。生涯学習を促進し、積極的に新しい知識や能力を習得する能力です。これは、次々と登場する新技術を習得するのにふさわしいスキルです。❞
本書では、メタスキルこそが「問題発見力」「的確な予測」「革新性」「技術活用力」といった現代に求められる力の土台であり、AI時代のビジネスパーソンに必須の能力であると結論づけています。
実は、サードエイジこそがメタスキル開発に適している
サードエイジとは、歴史学者ピーター・ラスレットが提唱した、人生を4つの段階に分ける考え方の3段階目にあたります。子育てなどの義務から解放され、自己実現に向かう“人生の最盛期”とされるこの時期に、本書はメタスキル開発の適性が高い世代として注目しています。
その理由は、「AIの価値は問いによって決まる」という視点にあります。
AIは膨大なデータをもとに的確な答えを導く力を持っていますが、何を問うべきか=問いそのものの創出は人間にしかできせん。そして、「価値ある問い」は、経験によってこそ生まれると本書は述べています。
この“経験”がなぜ問いの質を高めるのか。その根拠として、本書は以下の4点を挙げています:
1.洞察と理解の深化
人間関係や困難を乗り越えた経験から、当事者さえ気づかない本質的な問題や感情を読み取れる力が育まれる。
2.感情的なつながりと共感
他者との関係性の中で生まれる共感は、問いの視点を多様化・深化させる。
3.現実への洞察と実践的な問い
理想論に偏りがちなAIに対し、現実の文脈に根ざした実践的な問いを立てられる。
4.価値観と目的の形成
経験に裏打ちされた価値観は、問いに深みと独自性を与える。
こうした問いを生み出せる力は、年齢とともに蓄積される経験に比例することが多いため、サードエイジには明らかなアドバンテージがあると本書は結論づけています。
加えて、本書および私たちは以下の観点からも、サードエイジ世代を重要視しています:
・セカンドエイジ(働き盛り世代)よりも多様性があり、すでにメタスキル人材としての素養を備えている人が多い
・これまでそうした機会を得られなかった層も存在し、伸びしろが大きい
学びは年齢に関係なく可能であり、脳の可塑性も晩年まで保たれることがわかっている
・遅咲きで開花する知的才能もあり、「知的長寿」の観点からも注目に値する
❝メタスキルは未来を生きるすべての人にとって重要です。全員が習得すべきものですが、生きた経験によって価値ある問いを生み出せるサードエイジは、メタスキルの習得によってさらなる価値創出ができる可能性が高く、これからの組織において最も期待されるべき存在と言っても過言ではないでしょう。❞
企業がサードエイジに注目すべき理由
ここまで見てきたように、AI時代に必要とされるのは「メタスキル」であり、サードエイジはその開発に適した存在です。
ではなぜ、特に日本企業こそがこの世代に注目し、リスキリングに力を入れるべきなのでしょうか。
日本は、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進行している国のひとつです。総務省の統計によれば、2024年時点で50歳以上が人口の約半数を占めています。
2023年の労働力人口は約6,925万人と、前年比で23万人増加していますが、これは主に女性の就労増加によるもので、男性は実際に4万人減少しています。今後も、労働力人口が減少していくのは確実です。
2023年の就業者数を年齢10年刻みで示すと以下のようになります。
15~24歳 562万人
25~34歳 1114万人
35~44歳 1288万人
45~54歳 1631万人
55~64歳 1237万人
にもかかわらず、多くの企業では、50代以上になると一線を退く「役職定年制度」が一般的です。多くの人事部門では、将来性を重視し若手を中心に育成を行い、50代・60代の従業員については「給与に対してパフォーマンスが見合わない」と見られがちです。
しかし、これらの統計を見たとき、本当に50代60代を「お荷物」のように見なして良いのか、問い直す必要があります。
❝人事部門の担当者が「50代60代の従業員がお荷物で戦略を描けない」と思っているのだとしたら、その考えを改めるべきです。50代60代の従業員は、メタスキル人材に一番近い、これからの時代を切り開くことができる人材なのです。
50代60代の多くの人材をメタスキル人材に変えることができれば、日本企業にとって最大の武器となります。最大の「弱み」を最大の「強み」に変えることができるのです。これは、AI時代に日本が世界のトップに立てる逆転の戦略と言えます。❞
まとめ
テクノロジーが急速に進化し、AIがビジネスに深く入り込む今。
企業にとって本当に重要なのは、テクノロジーを“使いこなせる人”を育てることではなく、人間にしかない本質的な力をどう引き出し、活かすかという視点です。
その鍵を握るのが、豊かな経験を持ち、学び直しのポテンシャルを秘めたサードエイジ世代。
本書『逆転のリスキリングとサードエイジの時代』では、サードエイジがなぜ今必要とされるのか、そして彼ら・彼女らをさらに“価値ある人材”へと育成するための視点と手法が、実践メソッドとともに示されています。
本書は、人事・組織開発・経営に関わる方々にとって、これからの人材戦略を考えるうえでの新たな視座を提供してくれるはずです。
また、ハイパーアイランドでは本書と連動した実践プログラムとして、【サードエイジ リパーパスプログラム】も開講しています。まずは書籍を通じて、これからの人と組織の可能性を広げる第一歩を踏み出してみてください。
詳しい資料はこちらからダウンロード!

Hyper Island Japanチーム
北欧発のビジネススクール「Hyper Island」の日本チームです。
Hyper Islandのメソッドや思想をもとに、企業や個人の学びにつながる情報を発信しています。