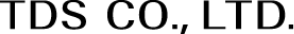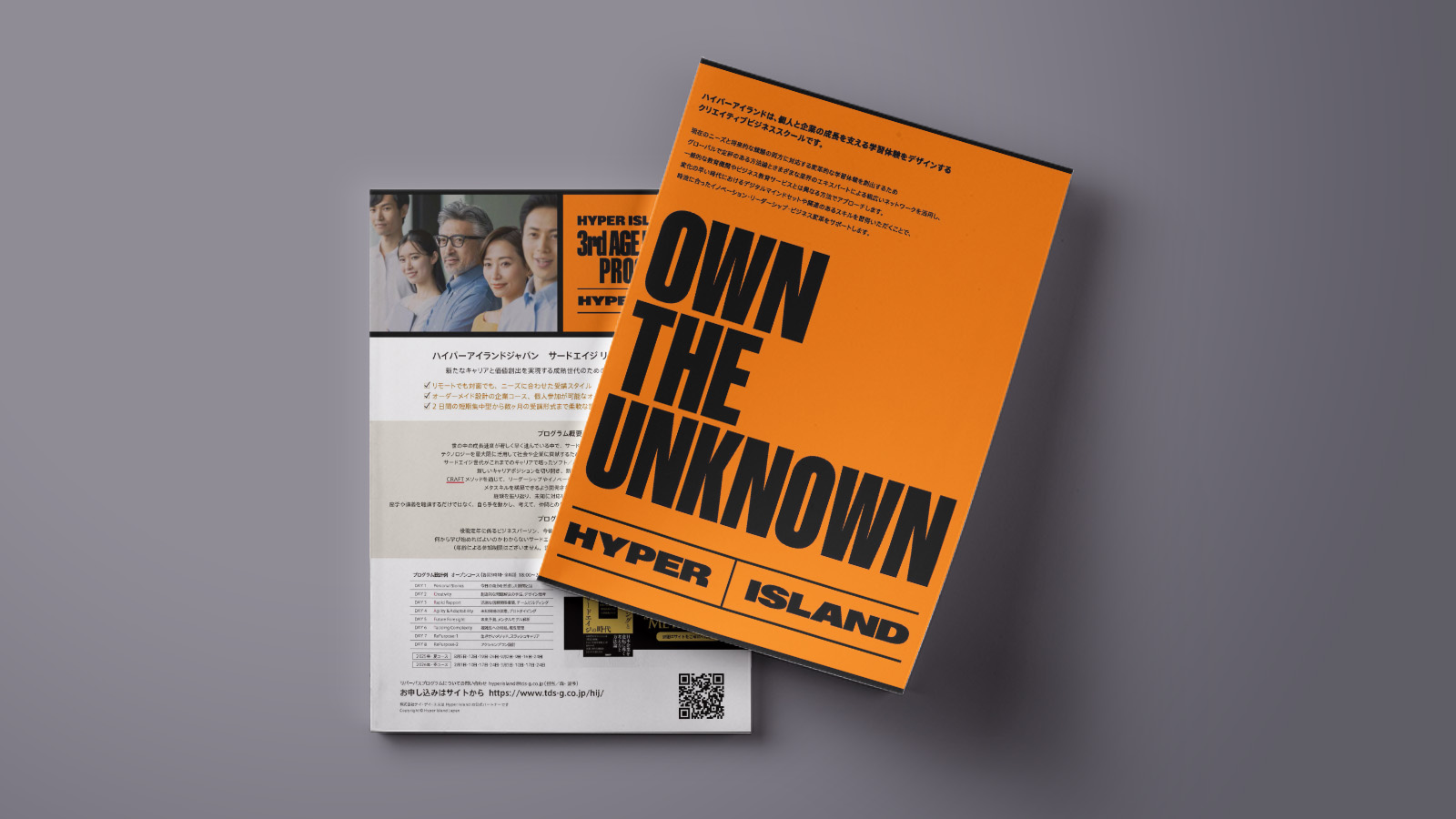ブランド戦略のトレンドとは?~選ばれるブランドのつくりかた~
ブランドは消費者との関わりを再定義しつつあります。
その中心にあるのは、AIによるパーソナライズ、高度なプライバシー基準、そして没入型テクノロジーの活用です。
本記事では、Aeroplane社が発行した『2025 Branding Trends Report』をもとに、これからのブランド戦略に影響を与える主要トレンドをご紹介します。
AIの活用によって、ブランドと消費者の関係が新しいかたちに変わりつつあります。
たとえば、AIはそれぞれの人の好みに合わせて、まるで自分のためだけに用意されたような体験を作ることができます。
こうした「ハイパーパーソナライゼーション」と呼ばれるアプローチを取り入れることで、ブランドはより自然で親しみのあるコミュニケーションができるようになり、AIが持つ創造力も最大限に活かせるようになります。
このような工夫は、ただ情報を届けるだけでなく、心の通ったつながりを生み出すきっかけとなり、変化の激しい市場の中でも、消費者のロイヤルティ(信頼や愛着)を育てることにつながります。
クリエイターとしてのAI
コカ・コーラの「Masterpiece(マスターピース)」キャンペーンは、AIと人間の創造性が融合した、視覚的に印象的なグローバルプロジェクトです。世界的な名画に命を吹き込むことをテーマに、さまざまなアーティストとコラボし、コカ・コーラのボトルが古典から現代アートの中に自然に溶け込むように描かれました。
AI技術によってアートがアニメーション化され、没入感のある映像体験を実現。アンディ・ウォーホルからフェルメールまで、美術館を舞台にコーラが手渡されていくストーリーを通じて、ブランドが時代や文化を超えて人々とつながる存在であることを象徴的に表現しています。
データ分析者としてのAI
Spotifyの「Only You」キャンペーンでは、ユーザーの音楽履歴や再生傾向をAIで分析し、高度にパーソナライズされたリスニング体験を提供しました。ジャンルの組み合わせやアーティストのペア、再生時間帯など、ユーザー固有の聴取傾向をもとに、個別のプレイリストやビジュアル表現を生成。
「Only You」は、こうした一人ひとりの音楽の旅を称え、SpotifyのAI技術の力を示すと同時に、ユーザーの嗜好を尊重することでロイヤルティを高める施策となりました。
クリエイター&データ分析者としてのAI
Nikeの「Design Your Own Shoes(自分だけのシューズをデザインしよう)」では、AIを活用して、ユーザーが色・素材・パターンを選んで自由にカスタマイズできるインタラクティブな体験を提供しました。
この高度なパーソナライゼーションは、AIアルゴリズムによってユーザーの好みを分析することで実現。リアルタイムで得られるデータをもとに、Nikeは商品開発を洗練させることができました。
この取り組みでは、ユーザーの選択傾向からインサイトを導き出し、一人ひとりに合ったデザイン提案を行うことで、より「自分らしい一足」を実現。ユーザーは自分の感性を反映したシューズを作る楽しさを味わえると同時に、ブランドとの絆を深めることが可能になりました。
音声検索やスマートアシスタントの普及により、消費者とブランドの関わり方が大きく変化しています。
利便性が重視される今、ブランドは音声技術を活用できるようデジタル戦略を最適化し、ユーザーのアクセシビリティとエンゲージメントを高める必要があります。
AI主導のインターネットインタラクション
AIは音声入力を即座に理解・処理できるため、プライバシーのポップアップや長いスクロールといった手間を減らし、スムーズで会話のような体験を提供します。AIアシスタントも進化を続けており、インターネット接続により、質問への回答だけでなくタスクの実行まで可能になっています。
こうした変化により、インターネットの利用は「検索する」から「話しかける」へと移行し、個人に合わせた音声ベースの体験が広がっています。そのため、音声技術が普及する中で、AIによる検索結果で見つけてもらうには、SEOの重要性がこれまで以上に高まっています。
AIによるパーソナライゼーションの高度化
次世代のインターネット体験は、単なる回答にとどまらず、AIがリアルタイムでユーザーに合った提案を行うことで、体験そのものを新しく定義しようとしています。
たとえば、出張の予定が入ったとき、AIアシスタントがその場でフライトの手配、ホテルやレストランの予約までを一度の会話でこなし、それらをわかりやすく整理したリストにまとめてくれる——そんな使い方が可能になります。
また、AIとのやりとりによって、株価の動向を分析したり、会議のスケジュールを自動で調整したりと、これまで手間がかかっていた作業もスムーズに進められるようになります。
こうしたAIアシスタントの機能がどんどん広がる中で、企業にとっては「どのような検索意図に応じて自社の情報が見つかるか」がますます重要になります。そのため、SEO(検索エンジン最適化)への取り組みはこれまで以上に欠かせなくなっています。
カスタマーサービスにおける音声技術の活用
現在、多くの企業がカスタマーサービスの効率化と顧客満足度の向上のために、音声技術を導入しています。
たとえば、音声操作に対応したAIアシスタントやロボットが、店舗内での商品検索や案内をサポートするなど、リアルタイムでの対応を可能にしています。
こうした即時性のあるサポートは、買い物体験をより快適にし、音声技術が業務効率の向上と顧客とのより深い関係構築に貢献していることを示しています。
音声操作によるスマートホーム機器
スマートホーム技術の広がりとともに、音声で操作できるデバイスが、家庭の自動化や日々の暮らしをより便利にする存在として注目されています。
たとえば、照明・暖房・セキュリティなどを「声だけで操作できる」機器が登場し、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携することで、家の中のさまざまな設備を簡単にコントロールできるようになっています。
こうした音声対応のデバイスが増えることで、家の管理がぐっと手軽になり、暮らし全体に統一感が生まれます。
これらは、将来的にさらに高度な家庭用ロボットへとつながる第一歩とも言え、今後の住まいの在り方を大きく変える可能性を秘めています。
進化する音声検索とSEO戦略の重要性
音声技術が進化するにつれ、効果的なSEO戦略の重要性はますます高まっています。
企業は、従来のテキスト検索とは異なる、会話形式の検索クエリに最適化したアプローチに適応する必要があります。
また、音声検索の約半数はローカル意図を含むため、ローカルSEOへの注力が不可欠です。
さらに、AI主導の検索プラットフォームが進化する中で、構造化データの活用などを通じてSEOを洗練させ、音声検索での可視性を高めることが鍵となります。
これらのトレンドを先取りすることで、ブランドはユーザーとの効果的なエンゲージメントを実現し、拡大する音声検索市場のニーズに応えることができます。
企業は、今や単に商品やサービスを売る存在ではなく、社会の価値観や人々の選択に影響を与える大きな力を持っています。その中で「倫理的マーケティング」は、消費者のロイヤルティを築くために欠かせない要素となっています。
もちろん、すべての企業が完璧である必要はありません。
けれども、誠実さや透明性を大切にする姿勢は、社会的な意識の高い現代の消費者の共感を得やすく、長期的な関係づくりにつながります。
本気でポジティブな社会的影響を生み出そうとする企業は、ただの提供者ではなく、業界や社会に変化をもたらす“担い手”となることができるのです。
Nikeのアドボカシー(社会的提言)活動
Nikeは、単なるスポーツブランドにとどまらず、社会とつながるブランドとしての姿勢を打ち出しています。
その一例が「Play New」キャンペーンです。
このキャンペーンでは、「スポーツは上手じゃなくてもいい、まずは楽しむことが大事」とする新しい価値観を提案。
「運動が苦手」「体型が気になる」「スポーツの経験がない」といった人々にも、身体を動かすことの喜びを広げようとしています。そして、誰もが参加できるスポーツのあり方を発信することで、インクルージョン(包摂)や多様性への配慮を自然に促しています。
Nikeはこのように、現代の社会課題に対して明確なメッセージを発信することで、企業としての責任ある姿勢を示し、消費者との信頼関係や共感を深めています。こうしたアドボカシー活動は、ブランドへのロイヤルティを高める重要な役割を果たしているのです。
サステナビリティを重視した取り組み
ユニリーバは、私たち一人ひとりの選択が環境に与える影響を考えるきっかけをつくるため、積極的にサステナビリティに関する活動を展開しています。
中でも、Dove(ダヴ)の「Sustainable Packaging(持続可能なパッケージ)」は代表的な取り組みです。
このプロジェクトでは、プラスチックごみの削減に向けて、100%再生プラスチックの使用や、持続可能な方法での素材調達を実現しています。
こうした活動を通じてユニリーバは、環境に配慮したライフスタイルの普及と、より意識的な消費行動の促進に貢献しています。
透明性ある目標と進捗の共有
Patagonia(パタゴニア)は、サステナビリティに関する自社の取り組みや成果について、透明性をもって発信することを大切にしています。環境への配慮をアピールするだけの“グリーンウォッシング”に対する消費者の疑念に、正面から向き合っているのです。
その姿勢を象徴するのが、「Buy Less, Demand More(買いすぎず、より良い選択を)」キャンペーン。これは、消費者自身が購買行動の影響を見つめ直し、より持続可能な選択をしていこうという呼びかけです。
活動の進捗も定期的に発信されており、企業としての責任ある姿勢を共有することで、「信頼できる企業を応援したい」という消費者の気持ちに応え、共に環境意識の高い選択を育んでいます。
これまで多くの企業は、「サードパーティクッキー」と呼ばれる技術を使って、ユーザーのネット上の行動を追跡し、広告やコンテンツを最適化してきました。
しかし現在、この技術はプライバシー保護の観点から廃止が進んでおり、マーケティングのやり方そのものが大きく変わろうとしています。
今注目されているのは、自社で収集するファーストパーティデータや、閲覧しているページの内容に合わせて広告を表示するコンテクスチュアル広告(文脈広告)など、よりユーザーのプライバシーに配慮した手法です。
これからの時代、企業には「ユーザーが納得して情報を提供し、その使われ方が透明である」ことが求められます。つまり、プライバシーを守りながらも、ユーザーに合わせた価値ある体験をどう提供するか。このバランスをいかに取るかが、ブランドの信頼と成果を左右する鍵となっていくのです。
サードパーティクッキーの代わりに注目される「ファーストパーティデータ」
サードパーティクッキーの廃止が進む中で、企業はこれまでのように外部の情報に頼るのではなく、自社で得られる「ファーストパーティデータ」を活用する方向にシフトしています。
たとえばコカ・コーラは、ロイヤルティプログラムやウェブサイト上のやりとりを通じて得たデータをもとに、ユーザーに合わせたパーソナライズ施策を展開。しかも、それをプライバシーに配慮した形で行っています。
Amazonも同様に、ユーザーの購買履歴や閲覧データをAIと組み合わせて分析し、個別に最適化されたキャンペーンを展開しています。
このように、ファーストパーティデータを活用することで、企業は信頼性のあるデータに基づきながら、効果的で精度の高いマーケティングを実現できます。
さらに、ユーザーの同意を得て活用することで、プライバシーへの配慮とエンゲージメントの向上を両立できるのです。
プライバシー重視の時代に注目される「文脈広告」
ユーザーのプライバシーに対する関心が高まる中で、ブランドはこれまでのように個人の行動を追跡する方法(=サードパーティクッキー)に頼らない、新しい広告の出し方を模索しています。
そのひとつが「文脈広告(コンテクスチュアル広告)」です。
たとえばニューヨーク・タイムズでは、読者が今読んでいる記事の内容に合わせて広告を表示する仕組みを導入しています。これは、ユーザーの過去の履歴や行動に依存せず、「今この瞬間の興味」に合わせた広告を表示できる手法です。
データの透明性が信頼を生む時代へ
データの使い方がますます注目される中で、「どうやってデータを集めて、どのように使っているか」をオープンにするブランドが、より多くの信頼を得る傾向にあります。
たとえば Apple は、「App Tracking Transparency(ATT)」という仕組みを導入。アプリがユーザーの行動を追跡してもよいかをユーザー自身が選べるようにしています。
このように「勝手に追わない」「自分で決められる」という姿勢が、信頼やブランドロイヤルティを高めているのです。
また Microsoft は、「プライバシー・バイ・デザイン」という考え方を採用。製品やサービスを設計する段階からプライバシー保護を組み込む方針を掲げ、法令遵守にも力を入れています。
このような透明性と法令遵守への取り組みは、企業が消費者の信頼を保ちつつ、変化する規制環境に対応していくために不可欠です。
拡張現実(AR)や仮想現実(VR)の技術は、消費者を深く引き込む没入型の体験を提供することで、マーケティングのあり方を変えつつあります。
これらの技術がより身近になる中で、ブランドは印象に残る体験を通じて、消費者の強いつながりを築くことが可能になっています。
ホログラフィックARと複合現実(MR)
MicrosoftやMetaといった企業が、専用のヘッドセットなしでも楽しめる3Dディスプレイの開発を進めており、ホログラフィックARの技術が急速に進化しています。
近い将来には、家庭やお店で等身大のデジタルアシスタントやブランドのインタラクティブなコンテンツを直接体験できるようになる見込みです。
AIを活用したホログラムは、その場でリアルタイムに説明やデモを行うことができ、まるで目の前に人がいるような臨場感のある体験を生み出します。
このような複合現実(MR)を活用したマーケティングは、デジタルと現実の境界をなくし、駅やショッピングモールなどの公共空間でも、印象に残るブランド体験を提供できるようになります。
バーチャル不動産とNFT体験
メタバースの広がりとともに、仮想空間上の「バーチャル不動産」への関心が高まっています。これを活用して、ブランドは自社専用のデジタル空間をつくり、特別なブランド体験を提供し始めています。
さらにNFT(非代替性トークン)を使うことで、消費者は限定イベントやデジタル商品へのアクセスが可能になり、ブランド側は希少性のある仮想世界を構築できます。
このように、VR(仮想現実)とブロックチェーン技術を組み合わせることで、消費者がブランドの仮想空間づくりに主体的に関わることができるようになり、より深いつながりが生まれています。
VRにおける香りと触覚の導入
ARやVRの技術は、見る・聞くだけではなく、「五感すべて」を使う体験へと進化しています。
たとえば旅行業界では、VRで海辺を体験しながら潮風の香りを感じたり、触覚ソックスで砂の感触を味わったりするようなサービスが登場するかもしれません。
すでにTeslasuit(テスラスーツ)やHaptXグローブのような機器では、全身で触覚を感じられる技術が試されています。また、OVR Technologyは「ビーチ」などの香りを再現する香り発生デバイス「ION」を開発中です。
こうした技術はまだ開発途中ですが、将来的には展示会や店舗、家庭でもリアルに近いVR体験が可能になり、マーケティングのあり方を大きく変える可能性を秘めています。
没入型マーケティングの未来:VRからスマートコンタクトレンズへ
Meta Questの高画質ディスプレイや視線を追う技術(アイ・トラッキング)の進化によって、VRを使ったマーケティングは、よりリアルでインタラクティブな体験ができるようになってきています。
さらに5Gの高速通信が広がったことで、ブランドはライブ配信型のVRコンテンツも届けやすくなり、より多くの人にリーチできるようになっています。
将来的には、Mojo Visionが開発中のスマートコンタクトレンズのように、メガネやヘッドセットが不要なAR体験が実現するかもしれません。
このような技術が実用化されれば、日常生活の中で自然にARを体験できる時代がやってくる可能性があります。
とはいえ、こうした次世代デバイスの開発にはまだ課題も多く、実用化にはもう少し時間がかかりそうです。
進化するソーシャルARとアイデンティティの表現
AR(拡張現実)の進化によって、私たちが製品と関わる方法が大きく変わってきています。たとえば、L’OréalやIKEAなどの企業は、バーチャル試着や自宅での製品のAR表示といった体験を提供しています。こうしたAR体験を通じて、消費者は自分の個性や好み(アイデンティティ)を反映しながらブランドと関わることができるため、より深いつながりが生まれます。
L’Oréalの「ModiFace」では、スマホやタブレットを使ってリアルタイムでメイクの仕上がりを試すことができます。IKEAの「Place」アプリでは、自宅に家具をARで配置してイメージを確認できるため、購入前にサイズ感や雰囲気をつかむことができます。
このように、ARは単なる広告手法ではなく、感情的なつながりや実用的な価値を提供する手段として進化しており、ブランドと消費者の関係性をより強く、深くしています。
インフルエンサーマーケティングは今、大きな転換期を迎えています。
従来のように有名人を起用するだけではなく、ブランドはキャンペーンにおける「本物らしさ」や「共感できる人柄」の重要性を再評価しています。
もちろん、有名インフルエンサーの影響力は今も健在ですが、近年ではより身近でリアルに感じられる人、つまりフォロワーとの距離が近く、信頼されている個人がより強い影響力を持つようになっています。
その背景には、フォロワーが「この人の言葉なら信じられる」「価値観が近い」と思えるような、自然なつながりや共通点を求めていることがあります。
こうした共感に基づくつながりこそが、今後のインフルエンサーマーケティングで高いエンゲージメントを生むカギとなっているのです。
リアルな人々を起用した本物志向のキャンペーン
アクティブウェアブランドのFabletics(ファブレティクス)は、「Power of Women(女性の力)」というキャンペーンで、一般の女性たちを主役に据えました。
選ばれたのは、体型も背景もさまざまな女性たち。従来のような完璧なモデルではなく、日常の中で強さや自信、個性を体現するリアルな女性たちです。
このキャンペーンでは、ボディポジティブ(自分の体を肯定する考え方)や自己肯定感の大切さがメッセージとして込められており、単なる広告ではなく、共感できるストーリーとして受け止められました。
Fableticsはこうした「本物の女性」をブランドの顔として打ち出すことで、リアルさと信頼感を演出。結果として、消費者との感情的なつながりを深めることに成功しています。
多様なインフルエンサーとのコラボレーション
Microsoft(マイクロソフト)は、活動家で教育者でもあるブリタニー・パクネット・カニンガム氏などとパートナーシップを組み、多様性や社会的な包摂(インクルージョン)への取り組みを発信しています。
このようなコラボレーションは、社会的な課題に関心を持つ人々とのつながりを強め、Microsoftのブランドイメージを「前向きな変化を後押しする存在」として印象づける効果があります。
また、人種や立場の異なる背景を持つインフルエンサーを起用することで、さまざまな視点を尊重する企業姿勢を伝え、「誰もが力を発揮できる社会を目指すブランド」としての信頼感を高めています。
社会的課題に取り組むインフルエンサー起用の効果
多くのブランドは、社会問題や環境問題への姿勢を示す手段として、インフルエンサーとのコラボレーションを積極的に進めています。
たとえば Reebok(リーボック) は、サステナブル素材を使ったシューズ「Cotton + Corn」のプロモーションにおいて、環境問題に関心を持つインフルエンサーとコラボしました。
この取り組みにより、リーボックの環境配慮への姿勢がより多くの人に伝わり、「エコ意識のあるブランド」としての評価が高まりました。
さらに、社会的インパクトに敏感な消費者層との信頼関係も強化され、ブランドとユーザーの間に共感や価値観の共有が生まれる結果となりました。
有名人とインフルエンサーを融合した遊び心あるキャンペーン
スキンケアブランド CeraVe(セラヴィ) は、俳優 マイケル・セラ が「実はCeraVeの創業者だった」というユーモア満載の陰謀論ストーリーを軸に、1か月間にわたるバイラルキャンペーンを展開しました。
このユニークな企画は 約450人のインフルエンサーによってSNSで拡散され、スーパーボウルのCM「Perfect (TODAY)」が公開される前に、なんと154億回ものインプレッションを記録。
CMでは、マイケル・セラが話すイッカク(narwhal)と登場したり、オーバーな商品紹介を披露したりと、シュールでコミカルな演出を展開。「CeraVeを作ったのは自分だ」とあくまで冗談めかして語るその姿が話題に。
彼の自然体なユーモアと親しみやすいキャラクターが、幅広い層の視聴者に好意的に受け入れられ、高いエンゲージメントと共感を生み出しました。
価値観に共鳴する“本物の”インフルエンサーを求めて
近年、ブランドは従来の「ただ有名な人を起用する」スタイルから離れ、自社の価値観と共鳴し、個人的なストーリーを語れるインフルエンサーとの連携を重視するようになっています。
こうしたインフルエンサーは、フォロワーにとってより身近でリアルな存在に映り、深い共感や信頼を生み出します。
つまり、インフルエンサーの人柄や信念がブランドと合っているかどうかが、これまで以上に重要になってきているのです。この傾向は、より誠実で意味のある消費者との関係構築へとつながっています。
ブランド戦略の未来とは
これからのブランド戦略に求められるのは、テクノロジーの進化と本物のつながりへの姿勢を組み合わせることです。
本レポートで紹介したように、
- パーソナライゼーション(個別最適化)
- 倫理的・社会的な取り組み
- 没入感のある体験
といった要素は、消費者とブランドの絆を深めるうえでますます重要になっています。
消費者の価値観に寄り添いながら、テクノロジーによる革新も取り入れることで、ブランドは変化の激しいマーケティング環境にも柔軟に対応し、長期的なロイヤルティを築いていくことができるのです。
レポートの全文(英語)は、こちらからダウンロードいただけます。
https://hyper-trends-2025.glide.page/dl/6471c6/s/a0ccac/r/0AHfLSPMC4r3M5qdqbPI
詳しい資料はこちらからダウンロード!

Hyper Island Japanチーム
北欧発のビジネススクール「Hyper Island」の日本チームです。
Hyper Islandのメソッドや思想をもとに、企業や個人の学びにつながる情報を発信しています。